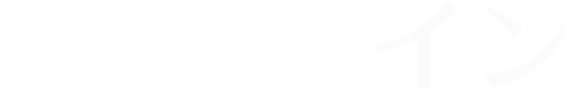アニマルクリニックフロンティア - 記事一覧
http://www.ac-frontier.jp/blog/
| 発行日時 | 見出し | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.01.03 |
Case.009


当院で実際に治療を受けられた犬・猫の歯科症例写真です。処置前と処置後の状態を比較してご紹介します。 ※症例写真・治療内容について #含歯性嚢胞 #歯原性嚢胞 #嚢胞 #未萌出歯 #短頭種 #埋伏歯 #下顎第1前臼歯
※治療当時の費用であり、病状や処置内容により費用が異なる場合がございます。
|
||||||||||||||||
| 2025.11.02 |
Case.008


当院で実際に治療を受けられた犬・猫の歯科症例写真です。処置前と処置後の状態を比較してご紹介します。 ※症例写真・治療内容について #破折 #露髄 #歯が折れた #歯が欠けた #複雑性破折 #根尖病変 #根尖膿瘍 #歯髄感染 #根尖性歯周炎 #歯内治療 #根管治療 #エンド
※治療当時の費用であり、病状や処置内容により費用が異なる場合がございます。
|
||||||||||||||||
| 2025.10.04 |
Case.007


当院で実際に治療を受けられた犬・猫の歯科症例写真です。処置前と処置後の状態を比較してご紹介します。 ※症例写真・治療内容について #口臭 #痛み #流涎 #歯周病 #慢性歯肉口内炎 #尾側口内炎 #破歯細胞性吸収病巣 #湾曲歯根 #全臼歯抜歯
※治療当時の費用であり、病状や処置内容により費用が異なる場合がございます。
|
||||||||||||||||
| 2025.09.16 |
Case.006


当院で実際に治療を受けられた犬・猫の歯科症例写真です。処置前と処置後の状態を比較してご紹介します。 ※症例写真・治療内容について #歯折れ #破折 #根尖性歯周炎 #精密根管治療 #歯内治療 #LAI
※治療当時の費用であり、病状や処置内容により費用が異なる場合がございます。 |
||||||||||||||||
| 2025.09.05 |
Case.005


当院で実際に治療を受けられた犬・猫の歯科症例写真です。処置前と処置後の状態を比較してご紹介します。 ※症例写真・治療内容について #歯周病 #摩耗 #根尖病変 #エンドペリオ #抜歯
※治療当時の費用であり、病状や処置内容により費用が異なる場合がございます。 |
||||||||||||||||
| 2025.08.31 |
歯周外科


8月に入ってから年末にかけて技術力向上の為の実習参加や学会、症例検討会への参加等で休診日が多くなり、皆様には大変ご迷惑をおかけいたします。 先日も東京にて日本獣医歯科学会主催のスケーリング実習に参加してきました。 そして、9/6(土)~7(日)は、東京で歯科医師の方々に混じって豚の顎を使った歯周外科実習に参加していきます。 歯周外科とは何でしょうか? 歯周外科とは、歯周病が進行し、通常の歯周基本治療(歯石除去など)だけでは改善が見られない場合に行われる外科的な治療法です。 歯周外科の主な種類 ◆フラップ手術(歯肉剥離掻爬術) ◆歯周組織再生療法 ・GTR法(組織再生誘導法): ◆歯周形成手術 ・結合組織移植術(CTG) ◆歯肉切除術 これらの術式は、人医療で実際に行われているものです。 当院でもフラップ手術、歯肉切除術などは歯科処置の際に行っております。 当院の獣医師は、過去に歯周外科に関する実技講習を受けており、日々研鑽しています。
歯科医師で歯周外科を行う人たちにとっては馴染のあるもので、こうやって歯周外科の技術を身につけていきます。 9月と10月は、病院を休診にして歯周病専門医・認定医から豚8頭を使って合計24時間にもおよぶ歯周外科技術の反復トレーニングをしてまいります。 9月以降は学会等の色々やることが多くブログの更新作業が鈍化します。 |
||||||||||||||||
| 2025.08.27 |
Case.004


当院で実際に治療を受けられた犬・猫の歯科症例写真です。処置前と処置後の状態を比較してご紹介します。 ※症例写真・治療内容について #歯周病 #歯肉退縮 #骨吸収 #抜歯
※治療当時の費用であり、病状や処置内容により費用が異なる場合がございます。 |
||||||||||||||||
| 2025.08.16 |
Case.003


当院で実際に治療を受けられた犬・猫の歯科症例写真です。処置前と処置後の状態を比較してご紹介します。 ※症例写真・治療内容について #歯周病 #残根 #残根抜去 #慢性根尖膿瘍
※治療当時の費用であり、病状や処置内容により費用が異なる場合がございます。 |
||||||||||||||||
| 2025.08.10 |
自立看板撤去のお知らせ


当院の目印になっていた自立看板を8/21(木)に解体・撤去することになりましたのでお知らせいたします。 昨今、老朽化した看板の落下等の事故が多発しています。 病院の看板はなくなりますが、病院自体は通常通り継続しますのですご安心下さい。 |
||||||||||||||||
| 2025.08.03 |
Case.002


当院で実際に治療を受けられた犬・猫の歯科症例写真です。処置前と処置後の状態を比較してご紹介します。 ※症例写真・治療内容について #乳歯抜歯 #乳歯晩期残存 #未萌出歯 #歯肉開窓術Before
※治療当時の費用であり、病状や処置内容により費用が異なる場合がございます。 |